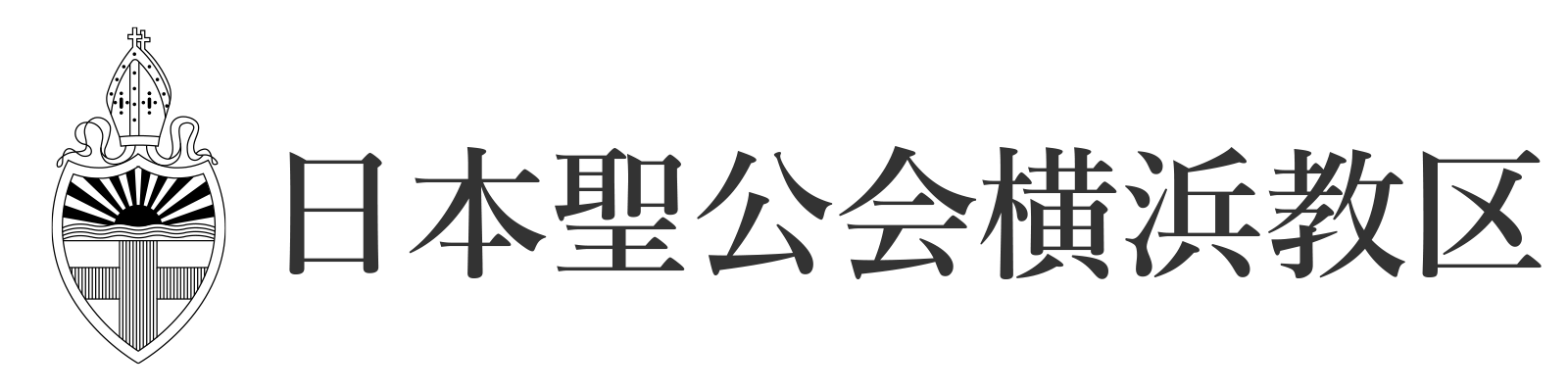巻頭言
聖霊降臨後第13主日(特定16)
特祷
旧約聖書
14あなたたちはだから、主を畏れ、真心を込め真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えていた神々を除き去って、主に仕えなさい。15もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今、あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを、今日、自分で選びなさい。ただし、わたしとわたしの家は主に仕えます。」
16民は答えた。
「主を捨てて、ほかの神々に仕えることなど、するはずがありません。17わたしたちの神、主は、わたしたちとわたしたちの先祖を、奴隷にされていたエジプトの国から導き上り、わたしたちの目の前で数々の大きな奇跡を行い、わたしたちの行く先々で、またわたしたちが通って来たすべての民の中で、わたしたちを守ってくださった方です。18主はまた、この土地に住んでいたアモリ人をはじめ、すべての民をわたしたちのために追い払ってくださいました。わたしたちも主に仕えます。この方こそ、わたしたちの神です。」
19ヨシュアはしかし、民に言った。
「あなたたちは主に仕えることができないであろう。この方は聖なる神であり、熱情の神であって、あなたたちの背きと罪をお赦しにならないからである。20もし、あなたたちが主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなたたちを幸せにした後でも、一転して災いをくだし、あなたたちを滅ぼし尽くされる。」
21民がヨシュアに、「いいえ、わたしたちは主を礼拝します」と言うと、22ヨシュアは民に言った。
「あなたたちが主を選び、主に仕えるということの証人はあなたたち自身である。」
彼らが、「そのとおり、わたしたちが証人です」と答えると、23「それではあなたたちのもとにある外国の神々を取り除き、イスラエルの神、主に心を傾けなさい」と勧めた。
24民はヨシュアに答えた。
「わたしたちの神、主にわたしたちは仕え、その声に聞き従います。」
25その日、ヨシュアはシケムで民と契約を結び、彼らのために掟と法とを定めた。
詩編
16 主のみ顔は悪を行う者に向けられ∥ 彼らの名は地から消される
17 主は正しい人の叫びを聞き∥ 悩みの中から救ってくださる
18 主は悲しみ嘆く者の近くにおられ∥ 失意の人を支えられる
19 正しい人は悩みが多い∥ しかし主はすべての悩みから助け出される
20 神は彼らの骨をことごとく守り∥ その一つさえ砕かれることはない
21 正しい人を憎む者は罪に定められ∥ 悪人は悪で身を滅ぼす
22 主は神に仕える人を贖い∥ 主に寄り頼む者を滅びから救われる
使徒書
福音書
66このために、弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。67そこで、イエスは十二人に、「あなたがたも離れて行きたいか」と言われた。68シモン・ペトロが答えた。「主よ、わたしたちはだれのところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。69あなたこそ神の聖者であると、わたしたちは信じ、また知っています。」
「信じ、知っています」
司祭サムエル小林祐二
今年の8月の主日は5回ありますが、そのうち1~4番目の主日(特定13~16)の福音書には、ヨハネによる福音書の6章24-69節が配分されています。6章1-15節でガリラヤ湖の「向こう岸」に渡り五千人を養われたイエス様は、「人々が来て、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、ひとりでまた山に退かれ」(15節)、その後弟子たちとともに「向こう岸」カファルナウムに戻られます。群衆も小舟に乗って後を追いますが、イエス様は「あなたがたがわたしを捜しているのは、しるしを見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ」(26節)と、群衆の行動理由を明言されます。しかし群衆はなお「見てあなたを信じることができるように、どんなしるしを行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか」(30節)と、物質的な根拠だけにしか目が向かず、イエス様が仰るように「わたしを見ているのに、信じない」(36節)のです。さらに「これはヨセフの息子のイエスではないか」(42節)と、悟ろうとする気配はありません。
特定16の6章60-69節は、これらの締めくくりとも言える個所で、多くの弟子たちが「実にひどい話だ」とつぶやき始め、ついに「もはやイエスと共に歩まなくなった」と伝えています。イエス様は残った使徒たち十二人に「あなたがたも離れて行きたいか」と尋ね、シモン・ペトロは「主よ、わたしたちはだれのところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると、わたしたちは信じ、また知っています」と答え、イエス様のもとに留まりました。
離れ去った多くの弟子たちと使徒たちとでは何が異なったのでしょう。イエス様と過ごした時間の長さだけでしょうか。
イエス様と群衆との決定的なずれは、「者」と「物」との捉え違いだと言えるのではないでしょうか。群衆の求めはパンという「物」に終始しますが、イエス様が差し出されるのはご自身そのものであり、ペトロの言葉にあるようにイエス様が「永遠の命の言葉」「神の聖者」であることに気づくよう、語っておられたのです。
自分の肉を与えることは、肉体の危険を意味します。「わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、いつもわたしの内におり、わたしもまたいつもその人の内にいる」と仰るイエス様のみ言葉には、身の危険をいとわないばかりか、それを裂いてお与えくださるという熱いみ心が込められているのです。それはわたしたちの罪の生贄としてご自身をささげられた十字架において完全に現され、また渡される夜にお立てになった聖餐のうちにも秘められています。聖餐はパンとぶどう酒という「物」ではなく、ご自身を裂いてお与えになるほどにわたしたちを愛してくださるイエス様そのものだということを思い起こしたいものです。
この原稿が皆さまの元に届く頃、コロナ禍が収束に向かい、諸教会の聖餐式が公開されていることを切に願います。そして飢え渇くわたしたちが、イエス様から離れず、永遠の命の糧を心で悟り、み心によって満たされ、潤されますように。
(清里聖アンデレ教会牧師)
欅の坂みち
+主教 イグナシオ
相手の話を集中して聞いた時に、後から疲労感を覚えることがあります。
それは、相手の語る言葉だけでなく、声のトーンや表情、そしてしぐさなどから、その背後にあるその人の訴えを漏らさず受け止めようとしているからなのではないでしょうか。
言葉一つにしても、その背後にあるその人の思いを汲み取ろうとしますと、聞く側は、その何倍もの思いを巡らしながら聞きます。手紙でいえば、行間を読むということです。
今、このコロナ禍にあっては、直接、人に会って話したり食事をしたりすることが制限されていますから、いっしょに教会に集まって礼拝をささげた後も、いろいろな人と言葉を交わすこともなかなかできません。
ズームを使った会議や研修会が行われるようになり、少しずつ慣れては来ましたが、そこでは、参加者同士が言葉を交わすことはなかなか難しく、直接会った時と同じではありません。
そうした中で今、改めて思うのですが、人と人とのコミュニケーションは、お互いを思いやることによって深められていくということです。
相手の思いを「こうかな、ああかな」と想像しながら思いやって、相手の訴えを受け止めていきます。
それは、言葉にならない相手の思いを受け止めるということであり、そこにいる相手の心に自分自身の思いを傾けて聞くということです。自分のところに届けられる情報を受け身でただ待つのではなく、五感を駆使して積極的に相手の思いに聞き入っていくということです。
こうしてお互いに相手を思いやっていく時、たとえ今のような状況にあっても、いえ、このような時であるからこそ、より強くそのことを意識しつつ、私たちはお互いにその交わりを更に深め合っていくことに努めて参りたいと思います。
※聖書本文は以下より引用しました。
聖書 新共同訳:(c)共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible Translation
(c)日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988